本書の想定読者は、生きづらいと感じている人、この社会にうまく乗れない人、のようです。見落としていたのですが、本書のサブタイトルは、「私」を生き直すための哲学、でした。
ところで、人は日々、人・物事との出会いを通じて、自分自身の世界像(世界の感じ・世界に対する構え)を編み直しながら生きています。当然のことながら、世界像の編み直しを促す人・物事との出会いは、本書で取り上げられているような、傷とか、自分の既存の価値観からの逸脱行為、といったことに限られるわけではありません。特に、日常世界での思い込みを、メタレベルの視点に立って虚構と認識することで、世界像は大きく変わります。以下、人間には自由意思があるという思い込みと、その虚構性の認識による世界像の変容について少し書きます。
■自由意志があるというのは勘違い
人間には自由意思がある(自分の意思決定・アクション選択を、自分が意識的にコントロールしている)というのは思い込みで虚構。ちなみに、脳科学や心理学を紐解かなくても、人間に自由意思が無いことは、次のような内省でもわかります。
【質問】
猛暑の中、エアコンが壊れてしまった。古くて修理不可のため、量販店に駆け込みどれを購入するか検討した結果、AとBの2機種が候補として残った。比較すると、AはBより安いが、BはAより納期が早い。迷った末、納期を優先しBを購入した。--- これはまさに自由意思があるということではないのか?
【答え】
確かに自由意思があるように思える。しかし、AとBのどちらかを選択/購入する、という意思決定は何を基準(物差し)にして行われただろうか?コストアップよりも、エアコン無しの寝苦しい夜をなるべく少なくするのが重要だと考えたからに決まってるだろ、と言われるかもしれない。でもそれでは何が基準なのかの回答になっていない。ここでよく考えてみると、XよりYを重要だと考えた、というのは実は、YよりXの方に違和感がある(XよりYの方が快である)ということが本質であることがわかる。つまり、違和感(快不快)が意思決定の基準になっている。さて、この違和感(快不快)は、意思決定する時、意識的にコントロールできるだろうか?残念ながらできない。なぜなら違和感(快不快)は湧いてくるもの、これまでの人生で蓄積された快不快の記憶に依存するものだから。となると、意思決定は、自分で意識的にコントロールできない<違和感(快不快)>に基づき行われていることになる。よって、自由意思は虚構。
■自由意思は虚構だというメタレベルの認識の中だけでは人間は生きられない
自由意思があるという思い込み無しでは、人間(のルール)社会は成立しません。
なぜなら、人々が何らかルールを設定してそれを遵守しようとする場合、自分(や相手)はそのルールを意識的に守ることができる、という思い込みを前提(虚構)しているから。そして、自由意思があるのにルールを守れなかったら、それは守れなかった人の責任だ、という思い込みも、自由意思があるという思い込みと一体です。さらに、人が達成感・充実感を得るのは、自由意思で何かに取り組んでいるという思い込みがあるからです。なので、自由意思があるという思い込みを無くしたら、人間社会は成立しない。
■自由意思(とそれに伴う責任)が幻想であることの認識のもたらすこと
虚構性を認識すると、世界が今までと違って見えてくる/感じられる。例えば、自由意思が幻想なのに、殺人犯を死刑に処すのは虐待だ。危ない人なら再犯防止のため治療するか、治療が無理なら隔離するのが合理的。そもそも、自分達に不都合な人は、抹殺して良いというメンタリティは、侵略戦争のメンタリティに繋がる。死刑は廃止すべき!という世界観が生まれてきたりする、といったことがあると思います。つまり、虚構を認識することで、虚構が変質し世界が違って見えてくる。さらに、虚構自体を生きる時と、虚構をメタレベルで意識しながら世界を捉える時(特に、責任が問題になる場面)を、適宜切り替えながら生活することも可能になる。だから、虚構の認識は、人間社会の変化の大きなトリガーになると思っています。
久永公紀『意思決定のトリック』・『宮沢賢治の問題群』
新品:
¥1,980¥1,980 税込
発送元: Amazon.co.jp 販売者: Amazon.co.jp
新品:
¥1,980¥1,980 税込
発送元: Amazon.co.jp
販売者: Amazon.co.jp
中古品 - 非常に良い
¥1,602¥1,602 税込
中古品 - 非常に良い
¥1,602¥1,602 税込
配送料 ¥320 4月21日-22日にお届け
発送元: 熊猫堂【お急ぎ便なら翌日or翌々日に届きます!】
販売者: 熊猫堂【お急ぎ便なら翌日or翌々日に届きます!】
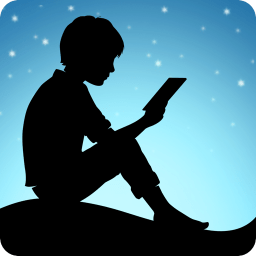
無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

利他・ケア・傷の倫理学 「私」を生き直すための哲学 (犀の教室 Liberal Arts Lab) 単行本(ソフトカバー) – 2024/3/27
近内悠太
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥1,980","priceAmount":1980.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"1,980","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"EIYVnkStfKzU5aM6KuXiTosfrUzArQSXyqo6ETXDJtYgtNxrWuXQBFwjAdRxVkxUeu7AiqTUx8gdGIhv13lYu2QPIveJoicGTw25lu7hlZtAVh7WMl%2FntWnVG3hvUfkyyRA4E9TzV08%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}, {"displayPrice":"¥1,602","priceAmount":1602.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"1,602","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"EIYVnkStfKzU5aM6KuXiTosfrUzArQSXIa422oFtF9MC09shCU%2BfUGXW0DWT41P2A0tjnQArrcvvcGTolQKu7RvF3LdwD2rloYv6xDpBOcR%2BkFqUzUKXm1L0AlugOVyII1pZ8rdGv9mjiYjSX0vjXhz6Z7Tm6myjqmbGYgWcJXv4RTjESELUnQ%3D%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"USED","aapiBuyingOptionIndex":1}]}
購入オプションとあわせ買い
「訂正可能性の哲学」がケアの哲学だったことを、本書を読んで知った。
ケアとは、あらゆる関係のたえざる訂正のことなのだ。
──東浩紀
人と出会い直し、つながりを結び直すために。
「大切にしているもの」をめぐる哲学論考。
「僕たちは、ケア抜きには生きていけなくなった種である」
多様性の時代となり、大切にしているものが一人ひとりズレる社会で、善意を空転させることもなく、人を傷つけることもなく、生きていくにはどうしたらいいのか? 人と出会い直し、歩み直し、関係を結び直すための、利他とは何か、ケアの本質とは何かについての哲学的考察。
進化生物学、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」、スラヴォイ・ジジェクの哲学、宇沢弘文の社会的費用論、さらには遠藤周作、深沢七郎、サン=テグジュペリ、村上春樹などの文学作品をもとに考察する、書きおろしケア論。『楢山節考』はセルフケアの物語だった!
「大切なものはどこにあるのか? と問えば、その人の心の中あるいは記憶の中という、外部の人間からはアクセスできない「箱」の中に入っている、というのが僕らの常識的描像と言えるでしょう。/ですが、これは本当なのでしょうか?/むしろ、僕らが素朴に抱いている「心という描像」あるいは「心のイメージ」のほうが間違っているという可能性は?/この本では哲学者ウィトゲンシュタインが提示した議論、比喩、アナロジーを援用してその方向性を語っていきます。」(まえがきより)
【目次】
まえがき──独りよがりな善意の空回りという問題
第1章 多様性の時代におけるケアの必然性
第2章 利他とケア
第3章 不合理であるからこそ信じる
第4章 心は隠されている?
第5章 大切なものは「箱の中」には入っていない
第6章 言語ゲームと「だったことになる」という形式
第7章 利他とは、相手を変えようとするのではなく、自分が変わること
第8章 有機体と、傷という運命
終章 新しい劇の始まりを待つ、祈る
あとがき
ケアとは、あらゆる関係のたえざる訂正のことなのだ。
──東浩紀
人と出会い直し、つながりを結び直すために。
「大切にしているもの」をめぐる哲学論考。
「僕たちは、ケア抜きには生きていけなくなった種である」
多様性の時代となり、大切にしているものが一人ひとりズレる社会で、善意を空転させることもなく、人を傷つけることもなく、生きていくにはどうしたらいいのか? 人と出会い直し、歩み直し、関係を結び直すための、利他とは何か、ケアの本質とは何かについての哲学的考察。
進化生物学、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」、スラヴォイ・ジジェクの哲学、宇沢弘文の社会的費用論、さらには遠藤周作、深沢七郎、サン=テグジュペリ、村上春樹などの文学作品をもとに考察する、書きおろしケア論。『楢山節考』はセルフケアの物語だった!
「大切なものはどこにあるのか? と問えば、その人の心の中あるいは記憶の中という、外部の人間からはアクセスできない「箱」の中に入っている、というのが僕らの常識的描像と言えるでしょう。/ですが、これは本当なのでしょうか?/むしろ、僕らが素朴に抱いている「心という描像」あるいは「心のイメージ」のほうが間違っているという可能性は?/この本では哲学者ウィトゲンシュタインが提示した議論、比喩、アナロジーを援用してその方向性を語っていきます。」(まえがきより)
【目次】
まえがき──独りよがりな善意の空回りという問題
第1章 多様性の時代におけるケアの必然性
第2章 利他とケア
第3章 不合理であるからこそ信じる
第4章 心は隠されている?
第5章 大切なものは「箱の中」には入っていない
第6章 言語ゲームと「だったことになる」という形式
第7章 利他とは、相手を変えようとするのではなく、自分が変わること
第8章 有機体と、傷という運命
終章 新しい劇の始まりを待つ、祈る
あとがき
- 本の長さ304ページ
- 言語日本語
- 出版社晶文社
- 発売日2024/3/27
- 寸法17 x 12 x 2 cm
- ISBN-104794974140
- ISBN-13978-4794974143
よく一緒に購入されている商品

対象商品: 利他・ケア・傷の倫理学 「私」を生き直すための哲学 (犀の教室 Liberal Arts Lab)
¥1,980¥1,980
最短で4月22日 火曜日のお届け予定です
在庫あり。
¥1,980¥1,980
最短で4月22日 火曜日のお届け予定です
在庫あり。
¥1,980¥1,980
最短で4月22日 火曜日のお届け予定です
在庫あり。
総額: $00$00
当社の価格を見るには、これら商品をカートに追加してください。
ポイントの合計:
pt
もう一度お試しください
追加されました
一緒に購入する商品を選択してください。
似た商品をお近くから配送可能
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
出版社より
利他・ケア・傷の倫理学

商品の説明
著者について
近内悠太(ちかうち・ゆうた)
教育者、哲学研究者。統合型学習塾「知窓学舎」講師。著書『世界は贈与でできている』(NewsPicksパブリッシング刊)で第29回山本七平賞・奨励賞を受賞。
近内悠太WEBサイト https://www.chikauchi.jp
教育者、哲学研究者。統合型学習塾「知窓学舎」講師。著書『世界は贈与でできている』(NewsPicksパブリッシング刊)で第29回山本七平賞・奨励賞を受賞。
近内悠太WEBサイト https://www.chikauchi.jp
登録情報
- 出版社 : 晶文社 (2024/3/27)
- 発売日 : 2024/3/27
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 304ページ
- ISBN-10 : 4794974140
- ISBN-13 : 978-4794974143
- 寸法 : 17 x 12 x 2 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 50,323位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 824位哲学 (本)
- - 1,359位その他の思想・社会の本
- - 1,708位評論・文学研究 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

1985年神奈川県生まれ。教育者。哲学研究者。慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業、日本大学大学院文学研究科修士課程修了。専門はウィトゲンシュタイン哲学。リベラルアーツを主軸にした統合型学習塾「知窓学舎」講師。教養と哲学を教育の現場から立ち上げ、学問分野を越境する「知のマッシュアップ」を実践している。『世界は贈与でできている』(NewsPicksパブリッシング刊)がデビュー著作となる。
カスタマーレビュー
星5つ中4.4つ
5つのうち4.4つ
51グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
イメージ付きのレビュー
星5つ中5つ
人の大切なものを大切にする
「世界は贈与でできている」が受け取るための本だとしたら、これは与える本、と著者は位置付けています。 「世界は〜」の本は、読後、しっくりきて、人に何かしたり、してもらったりする日々のやりとりへのハードルが低くなりました。 大袈裟に遠慮することなく、笑顔で受け取る。 さらに人のために何かをすることも受け取られるかどうかは重視せず、気軽に手を差し出すことができるように。 ただ、ここに起こりうるのが「押し付け」や「ありがた迷惑」な状況。そんなふうになるのはなぜなのか、が書かれています。 まさしく「あなたのために」という考えがその根底にあると言います。 誰かのためになることをしたい、という気持ちは社会性があるからこそ生き残った人間には基本的に装備されている。その気持ちを大切に、なおかつ目の前にいる誰かのために何かをするなら、この本をまず読もう。 電車で席を譲ったのに拒絶された経験がある。あの恥ずかしい経験を、恥ずかしいもので終わらせないヒントがこの本にはあります。
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます
申し訳ありませんが、エラーが発生しました
申し訳ありませんが、レビューを読み込めませんでした
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2024年5月10日に日本でレビュー済みAmazonで購入
- 2024年7月3日に日本でレビュー済みAmazonで購入ここ数年のトレンドともいえる「利他」「ケア」について論じられた本です。進化生物学(進化的適応環境)などの視点にまで遡って「必然性」を語ることにはじまり、筆者なりの利他やケアについての定義付けが丁寧に行われます。
中学入試に出題される可能性があると思って購入しました。
多様性の現代を善意が空転する時代だと定義し、一人ひとりの大切なものに違いのある現代の特徴をふまえない利他は「押し付け」や「道徳の暴走」だと断じます。ならば、私たちはどのようなことを意識し、「大切なものこそ見えない」日常を生きていけばよいのか。そんなことを考えていく「種」となる本だと思いました。
- 2024年8月27日に日本でレビュー済み多くの気づきをもたらす良著だとは思いますが、気になる点も同じくらいありました。
何よりも、利他を為される側の視点が欠如しているのが気になりました。
利他を為す側が利他を通じて新しい劇を始められる一方で、利他を為される側は新しい劇を始める契機を奪われているのではないか?
村上春樹のダンスダンスダンスを引用して、踊り続けることの重要性を説かれているが、利他を為される側にとってそれは、利他を為す人の掌で踊らされ続けるということを意味しないか?
あるいは、有頂天ホテルやカフカの逸話を引用して、利他的な嘘により劇を止めないことを肯定的に描いているが、その行為は利他を為される側をトゥルーマン・ショー的状況に押し込んで真実に気づく契機を奪うことにならないか? そのやさしさは偽善ではないにしても、とても残酷なものになり得ないか?
そもそも、利他によるセルフケア(という利己)、という回路は倫理的にも大きな矛盾を孕んでいないか?
- 2024年3月27日に日本でレビュー済みAmazonで購入前著の衝撃をきっかけに介護に転職し、自分自身、とても自由になれた実感を得ていたので「ケアについて書く」という本書の出版を心待ちにしていました。
一気に読ませて頂き、また大きな励ましと勇気を頂いた気持ちです。この獅子吼のあたり、特に好きです。
ーー
あなたが不合理性と不確実性の海へ飛び込むとき、その姿を美しいと思ってくれる人がいる。その人のために飛べ。言語ゲームを、劇を、書き換えよ。(p174)
ーー
またいつか「手放す」「諦める」のお話しも拝読できるのを楽しみにしています。
- 2024年7月17日に日本でレビュー済みAmazonで購入社会経験のない学者が言葉遊びをしているだけの本というのが、私の評価で、これを完読するにはかなりの忍耐が必要でした。例えるなら、脱線したまま走り続ける列車に乗っているような不快感です。
ただ、感じ方、捉え方は、人それぞれだと思いますので、その内容が各人にとって有意義なものであればそれで良いと思います。そもそもこのテーマは共感を求めたり、求められたりすること自体が相応しくないからです。たとえ私のような捉え方をする人にとっても、一度は読んでおくことに価値はあるだろうと思っています。
- 2024年10月4日に日本でレビュー済み〈まえがき ー 独りよがりの善意の空回り〉では、次の意味深な言葉で始まります。
一人ひとりがそれぞれの物語を生きている時代であることに、やさしさがすれ違う理由がある
僕らはしばしば劇を間違えるが、劇を変えることも演じ直すこともできる
暗示的ではあるけれども漠としたこのフレーズを読み解く「物語」が本書であり、ここにすべてが
言い表されていることをあとで知ることになります。
そもそもタイトルにある「利他」「ケア」「傷」とは何かを、近内さんは定義づけしています。
利他:自らの適応度を下げてまで、他の個体の適応度を上げる行動
ケア:他者の大切にしているものを共に大切にする営為全体
傷: 大切にしているものを大切にされなかった時に起こる心の動きやその記憶
ここに通底するキーワードは、「大切にしている」です。
本書のテーマについて考えることが重要になっているのは、時代背景です。
ひとつは、「多様性」の時代です。多様性が顕在化し、多様な生き方が認知されつつあります。
もうひとつは、AIに代表される科学やテクノロジーの驚異的な進歩です。
日本という同調圧力が強い国においては、まだまだ個人が「大切にしているもの」を大っぴらに
開示することは少ないですが、心のうちでは、わかりあえなさを痛感したり、諦らめの気持ちを
もっていたりします。わかりあえないことをわかるところから始めるしかありませんが、そこで
とどまっていては、私たちの傷は癒されません。
テクノロジーについていうと、人間の知性を補い凌駕することはできても、すれ違いのギャップを
埋めることはできません。なぜなら、ケアで重要なのはテクノロジーではなく、物語だからです。
この本の後半は、ヴィトゲンシュタインの言語ゲームを適用した解説になるため、馴染みのない
人(私もその一人)には難しいかもしれません。
ただ、最終版に提示される著者の提言は圧巻で読みごたえがあります。
存在の肯定。「あなたは何も間違っていない」と示すこと。これがケアの本質です。
ケアが為されるとき、そこで物語が切り替わる。傷の物語が祝福の物語へと変わる。
あまりにも理想論すぎるかもしれませんが、私たちが他者との関係性をより良いものとして、倫理
的にもより善い世の中にしているためには、避けて通れない道を示しています。
さらに著者の慧眼は、ケアを私たちの多くが理解している利他の概念を越えて、”他者の傷に導か
れて、ケアを為そうとするとき、自分が変わること” と説いている点にあります。一言でいうと、
「セルフケア」です。昨今、「セルフ・コンパッション」という考えが出てきていますが、近しい
概念です。他者を救う(ケアする)ためには、自分という「他者」を救うことからしか始まらず、
この域に達すると利他と利己(自己)はほぼ同じものになります。
コーチを職業としている関係上、本書の中で大きな気づきを得た文章を蛇足ですが下に記します。
自己変容とは、自らが従っている規律を移動してしまう現象の別名で、それは自己犠牲ではない
自己犠牲とは、私が変わらないままで何かを手放すことだ
「現在の私」を肯定できないから、過去を肯定することができないのだ
私の過去は、現在の私という立脚点からのスポットライトに照らされる
生きにくい時代に見えますが、考え直すなら、本来の人として「生き直す」ことが純粋にできる
時代が到来しているとも言えそうです。
深い洞察へと誘う本書に出会えたことに感謝です。















